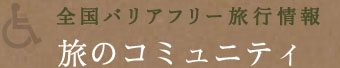ハダル@矢野です。
今回は、「福耳」について調べてみましたので、ご紹介します。
私自身は、どちらかというと福耳っぽいのですが、まだ、お金持ちにはなっていません。
皆様は、どうですか?
福耳といえば大黒天。耳たぶの上に米粒が乗るくらい上向きになっています。
福耳とは、耳たぶが大きく肉の厚い耳のことをいいます。
大黒天のように耳たぶが大きくふっくらしている耳で、
金運や福運があるとされたため福耳と呼ばれ、福相だといわれています。
福耳の中でも、「耳たぶが上向きになっている」タイプと「耳たぶが真下に垂れ下がっている」タイプがあり、
耳たぶの上に米粒が乗るくらい上向きになっている形が最も良い福耳とされています。
大黒天、恵比寿、布袋尊は、七福神の中でもとりわけ福耳です。
福耳といえばお金持ちのイメージが強いのですが、その場合の福耳は耳たぶが上向きになっているタイプです。
昔から、「福耳の人はお金持ちになれる」「お金持ちには福耳の人が多い」といわれています。
福耳だからお金持ちになったのか、お金持ちには福耳が多いからそうなったのか、
まるで「卵が先か鶏が先か」のようですが、福耳と金持ちが結び付いたのには理由があります。
福耳の代表といえる大黒天は、財宝・開運の神様で大変立派な福耳をされています。
また、商売繁昌や豊漁・豊作の神様とされている恵比寿、福徳の神様とされている布袋尊など、
お金や財産に関わる神様は立派な福耳をされています。
そこで金運や財産運を司る神様と同じ福耳をしていれば、縁起が良く、お金に困らないと考えられるようになりました。
仏像の多くが、耳たぶが真下に垂れ下がっているタイプの福耳です。
福耳には、耳たぶが真下に垂れ下がっているタイプもあり、
耳たぶが大きく垂れている人は偉人、聖人の相だといわれています。
お釈迦様などの仏像は、耳が大きく肩に近いほど垂れ下がっており、
孔子などの偉人もそのような耳が多いです。
福耳の有名人・芸能人ベスト3
・枝野幸男さん
・浅田真央さん
・松井秀喜さん
あんまり、気にして見た事がなかったので、あっ、そうなんだと思いますね。
それと、福耳は遺伝するそうですよ!
耳の形状は、大きさ、厚み、立ち具合などが人それぞれ違います。
成長に伴い耳の形状が変わることもありますが、
多くは遺伝するとされているので福耳も遺伝によるところが大きいようです。
それで、お金持ちの家系はずっと財閥なのでしょうかね。
残念ながら、福耳でない方は自分の努力で金持ちになるしかないようです。
周りの人を気をつけて見回して見て下さい。新しい発見があるかもね♪
ハダル@矢野です。
厳寒の中、植物は、早春の開花に向けて、着実に準備をしているようで、
我が家の梅の木にも蕾がたくさんついています。
今年は、梅の実もついてくれるのではないかと、今から楽しみにしています。
石見銀山では江戸時代に、鉱山病予防として防塵マスクが考案されたそうで、それがこの『福面』なんだそうです。
絹素材の周囲を鉄で覆って真ん中にも鉄を通した、今でいう3Dマスクみたいな感じですね。
機能性も考えられていて、生地には柿渋が塗られていて消臭や殺菌の効果もあったそうです。
しかも、内側には梅肉が挟んであったから驚きです!
梅干しの酸の力が、粉塵や灯りの煙を防いでくれると考えられていたそうです。
さらに、日本でマスクが使われ始めた資料として明治初期の1879年の広告が見つかっているそうですが、
それ以前の資料は確認されていないので、もしかすると石見銀山の『福面』が日本最古のマスクかもしれないってこと?!
本来は、「覆面」と書くところを縁起の良い『福面』にするとは、どんな意味を託しているのかは想像できます。
「福の地」と呼ばれただけあって、石見銀山で採れた銀鉱石を『福石』と名付けたり防塵マスクを『福面』と呼んだりと、
銀山の人たちは幸福を願って暮らしていたんでしょうね!
“福のある町 石見銀山” 皆さんも ぜひ訪れてみてはいかがですか?
また、株式会社ロッテは11月9日(火)、
小梅ブランド初となる島根県とのコラボ商品「小梅のど飴(袋)」を発売いしました。
商品パッケージに描かれた小梅ちゃんは、今回一風変わったマスクを装着しています。
これは、江戸時代終わりごろに備中国笠岡(現在の岡山県笠岡市)の医師・宮太柱(みや・たちゅう)が
多くの鉱山作業員が困っている姿を見て考案した"日本最古"のマスクです。
「福面(ふくめん)」と名付けられたこのマスクの内側には梅肉が挟まれ、
当時石見銀山で作業した人に重宝されたといわれています。
皆様も一度購入してみては、いかがですか!
ハダル@矢野です。寅年最初の投稿になります。今年もよろしくお願いします。
トンガの海底火山の噴火で、津波(?)が太平洋各地に影響を及ぼしましたね。
日本でも奄美大島や太平洋側には1.2mの津波(?)が押し寄せ、漁船などの被害がでたそうですが、
幸い、人命にまでは被害がなく、ほっとしたところです。
地震がなくてもこのような災害が発生するなんて・・・。
また、今日は、あの、阪神・淡路大震災発生から27年になりました。
災害は、いつでも起きうることに改めて、気づかせてくれる一日となりそうです。
さて、今日は、「大寒卵」でパワーアップと寒中を乗り切るという話題です。
一年で最も寒さが厳しいと言われる大寒の21日にこだわった卵が通信販売やスーパーマーケットでも
販売されると思います。
それでは、なぜ、大寒たまごは効き目があるのでしょうか?
「寒さに耐えて産まれた卵は滋養豊富で栄養価が高いといわれる」、「風水では大寒の日に産まれた卵を食べると、
体内に金運と幸運の種が宿るといわれる」などの説明が一般的に言われている事です。
お値段は、少し高めで、10個入りパックで350円前後のようです。
値上がり率の低い優等生にしては、少し高めですが金運と健康がアップすると言われれば安いのかもしれませんね。
少し「寒卵」について調べてみました。
中国では、大寒の頃に鶏が卵を産み始めるとして、「鶏始乳」(にわとり はじめて にゅうす)といい、
日本では寒の終わりごろ(1月30日ごろから、立春まで)を同じ漢字で(にわとり はじめて とやにつく)と読み、
「鶏が卵を産むために寝屋につく」といわれるそうです。
生き物が寒さ厳しい時期を乗り越え、無事に春を迎えて、新しい命を次代へつなぐという力強い言葉です。
「寒の内に鶏が産んだ卵を食べるとその年はお金に困らない」そうです。
その中でも特に大寒に産んだ「大寒卵」は、金運上昇パワーが最も大きいといわれています。
この時期の卵は滋養があって縁起ものだからだそうですが、「寒卵」は、季語になる
ほど、古くから滋養に富み、冬季間の希少で貴重なたんぱく源として、大切に食されていたようです。
もうすぐ大寒です!
同じたまごを買うなら21日(木)まで待って少し多めに食してみたらどうでしょうか?
まだまだ節分までは時間がありますので、何回かは貴重なたまごを食べて、
オミクロン株が猛烈な勢いで、日本全土に襲い掛かっていますが、乗り切れるかもしれません。
![]()