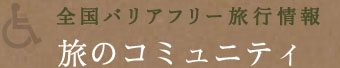ハウル@矢野です。半月ほど前の寒波はなんだったのでしょうか?昨日は、22度にもなった松江市です。寒暖差が大きく衣服の選択も大変な季節ですね。
今回は、日本で最長の路線バスの話題です。
それは、全長167キロ、停留所数は166の路線で、奈良交通の「八木新宮特急」で、高速道路を走らない日本一長い路線バスです。近鉄大和八木駅(奈良県橿原市)とJR紀勢線の新宮駅(和歌山県新宮市)を結ぶこの路線。所要時間「大和八木まで約6時間40分」うち10分~20分の休憩時間3回を含みますが、運転手さんは交代しないで一人で運転します。
バスは、1日3往復します。新宮駅発は午前5時53分、7時46分、9時59分の3便になります。
バスは、あっという間に市街地を抜け、雄大な紀伊山地へと分け入ります。熊野川沿いの国道168号を順調に北上して行きます。およそ1時間で、川湯、湯の峰の温泉街へ着きます。普通の車でも運転が難しい曲がりくねった道を、ベテラン運転手が、いともたやすく進んで行きます。 バスはずんずん山道を進み、高度を上げていきます。車良いが気になる方は、酔い止めは必需品ですね。奈良~和歌山の県境を越えて走って行きます。東京23区よりも広い日本最大の村、奈良県十津川村です。
改良された国道のバイパスを通らずに集落がある険しい旧道を右に左に。バス旅ならではの景色が続きます。
出発から2時間10分。やがて、十津川温泉へと入って行きますが、まだ行程の半分にもなりません。
1時間後、「上野地」で2回目の休憩です。ようやく半分を超えました。ここでぼーっと逡巡する暇はありません。日本有数の長さを誇る歩行者用つり橋「谷瀬のつり橋」の最寄りのバス停です。約20分の休憩時間に急げば往復できるらしいのです。
清流にかかるつり橋は長さ297メートル、高さ54メートル。想像以上のスケールで脚がすくみますが、早くしないとバスがてしまいまする。
再々出発したバスは、十津川を横目に北上を続けます。車窓を凝視していた目にも疲れが見えてきます。睡魔に負けそうになりますが、ほっぺをつねって気合を入れ直す。
やがて紀伊半島の分水界(熊野川水系と紀の川水系)でかつての難所だった天辻峠をトンネルで抜け、五條市へと向かいます。
バスは標高640メートルから一気に山を下ります。五条駅に到着です。
近くの五條バスセンターで3回目の休憩を取り、バスは最後の力走に備えます。 ラストスパートは、商業地や住宅地などを走ります。交通量が多く、乗客の入れ替わりも激しくなります。
やがて、車内に最後のアナウンスが響きます。「次は終点、大和八木駅」。
料金表示を見ると、整理券「1」は5250円(ちなみに最後は「109」で190円)です。
【16:37 167キロ 大和八木】
車内でも運賃を支払うことはできますが、通常の運賃(大和八木駅から新宮駅まで6,190円)よりお得になる「168バスハイク乗車券」(国道168号線を走るからこの名前がついているようです)がおすすめです。料金は5,250円です。しかもこの乗車券は2日間有効で途中下車可能。よって1日目は温泉地で宿泊し、2日目本宮大社に参拝するなど、楽しみ方に幅が出るのです。ただ、注意点もあります。このチケットは奈良交通社の窓口だけで販売しており、バス車内では購入できません。そして、逆方向に戻ることもできません。
以上は、実際に乗車した方の感想です。私の住む島根県にあるJR三江線は今月を最後に廃線となります。バスによる代替輸送となる予定で現在急ピッチで停留所の整備が行われています。このバスに乗車するときっと上記のような路線になるのでしょうね。路線バスは、また、列車と違い、空間も狭く人々の方言も変わって来るところなどそうゆったりとした座席ではありませんが、スピードも比較的にゆっくりですね。
ハウル@矢野です。日本列島は大荒れで松江でも大きな看板が落ちたり、駐車場のブロック塀が倒れたりして、車のフロントガラスが割れたりの被害がありました。皆さまの地方はどうでしたでしょうか?
ところで、3月3日と言えば勿論、ひな祭りですよね。また、この日は一年に5回ある節句の一つです。こちら松江では、月遅れで4月3日がひな祭りとなりますので、まだお雛様を飾っていないのではないかと思います。
節句とは、暦の上で節目になる日のことをいいます。まずは1月7日(人日の節句)、3月3日(上巳の節句)、5月5日(端午の節句)、7月7日(七夕の節句)、9月9日(重陽または菊の節句)です。節句は縁起が良く、お祝い事に向いている日だと考えられています。また、奇数が重なる日は、邪気をはらうことができるとも伝わっています。
昔から、といっても一般庶民に浸透したのはこれも江戸時代からだそうです。そもそもは、宮中の行事として様々な仕来たりは中国から伝わったという事です。子どもの誕生を祝い、邪気をはらって健やかな成長を願うために節句を祝います。
女の子の伝統行事「ひな祭り」の由来や意味をちょっとだけ紹介します。「ひな祭り」と言えば、雛人形を飾り、ちらし寿司やハマグリのお吸い物を食べて女の子の健やかな成長を願う伝統行事ですね。
しかしこのひな祭り、元は今とは少し違う行事だったのをご存知でしょうか。ひな祭りの起源は、季節の節目や変わり目に災難や厄から身を守り、よりよい幕開けを願うための節句が始まりとされています。
また、ひな祭りに欠かせないひな人形も、昔は飾るのではなく川に流されていました。この風習は全国各地で見る事が出来ます。こちら出雲地方でも出雲市の高瀬川で流し雛や安来市広瀬町ではお雛様を飾って一般の人への公開したりとイベントがあります。
ここでは、長くなりますので、菱餅の重ね方と色について書きますね。
ひな祭りの原点は、中国の「上巳の節」です。中国では、上巳節に母子草(ははぐさ)という草が使われた緑色の団子を食べていました。
母子草は、強い香りがあるので、邪気を祓うとされたのです。 日本では、母子草が手に入りにくく、よもぎ団子を食べていました。
緑だけでなく、他の色が加わったのは江戸時代初期からです。
まず、子孫繁栄や長寿になる事が出来る実だと言われる“菱(ひし)の実”を入れた白い餅が加わります。その後、明治時代に魔除けに使われる赤を加えて三色が定番になります。
色の意味
菱餅 色
ピンク(赤)
赤は魔よけのクチナシが使われている事から、魔よけの意味があります。
白
繁殖力の強い水草になるヒシの実が使われていることから、子孫繁栄や長寿の意味があります。
緑
ヨモギ(元々は母子草)は、強い香りで邪気を祓うとされています。
そして、菱餅の色の重ね方は、下から『緑→白→ピンク』が多いようです。
「残雪の下には(見えないけれど)新芽が芽吹いていて、雪の上には桃の花が咲いている」という、状況を表しているといわれています。
小さい女の子にはどのように説明すればわかってくれるのでしょうね。こういった事を正しく伝えて行く事も私たち大人の責任ですね。
![]()